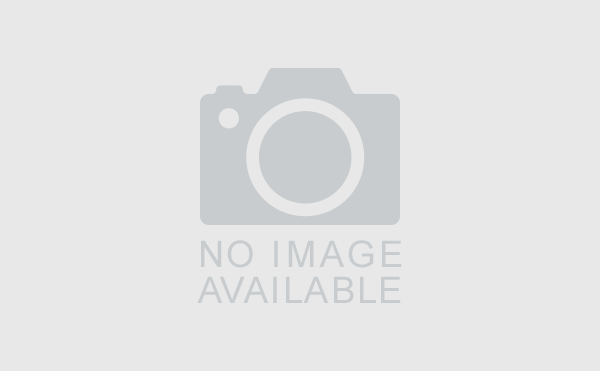「性の起源」
爬虫類や魚類の多くの種が無性生殖により雄の遺伝子無しで自己複製を行います。これは各個体それぞれが遺伝子を伝承でき子孫を増やすことができるといったコストのかからない方法です。一方、有性生殖(二細胞融合)は無性生殖に比べはるかにコストがかかります。相手となる生命体が必要となり、その相手を奪い合うエネルギーも相当なもので、かつ卵子が精子を捕食して結合に成功しなければなりません。しかも自分の遺伝子は半分しか伝えることができないのです。それでもなお有性生殖は淘汰されず地球上で最もポピュラーな生殖法となっているのは何故かといった問いにこれまでのところ明快な答えはなく、どちらかといえば減数分裂(注1)による遺伝的多様性に注目が集まっていました。2025年4月にヨーク大学の研究者からこの問いに対する新たな見識が提出されていますので紹介させていただきます。内容をごく簡単に要約すると、私たちが日常的に享受している繁殖システムは飢餓等の危機的環境下におかれた単細胞どうしが合体することにより大きな細胞質容積を得て過酷な状況を乗り越えられるよう進化したというものです。その時「せっかく合体したんだから、ついでに遺伝子も交換しようぜ。」的な意思の疎通があったかどうかは定かではありませんが、細胞の容積が増すことで生存率がどれほど上昇し、細胞融合を促進させるのかといったことを数理モデルで検証しています。これは単細胞真核生物において有性生殖は環境ストレスによって引き起こされることが多いという経験的観察とも一致しています。東日本大震災発生後、結婚願望が高まる「震災婚」という現象が話題に上ったことがありましたが、このモデルからなんとなく理解できるような気がします。
(注1)減数分裂(meiosis)
生殖細胞(精子や卵子)を作る際に起こる細胞分裂のことで染色体数が元の細胞の半分になります。これは染色体数が一定に保たれるために必要な過程であり減数分裂は2段階の分裂過程を経て最終的に4つの娘細胞を生成します。それぞれの娘細胞は元の細胞の半分の染色体数を持つことになり染色体の組み換え(遺伝子の交換)が起こり遺伝的多様性が生まれる結果となります。
Published: April 8, 2025 2025年4月8日(最新版)
Author Information
Xiaoyuan Liu1*, Jonathan W. Pitchford12 and George W. A. Constable1
1Department of Mathematics, University of York, York, North Yorkshire, United Kingdom
2Department of Biology, University of York, York, North Yorkshire, United Kingdom